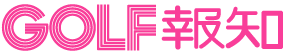日本プロゴルフ史上最初のプロ競技、第一回日本プロ選手権は1926年7月4日、大阪・茨木市の茨木カンツリー倶楽部に関西の福井覚治、村上伝二、越道政吉、宮本留吉、関東の安田幸吉、関一雄の計6人のプロゴルファーが出場、1日36ホールストロークプレーで争われた。前年、出来上がったばかりのコースに1日中雨が降り最悪のコンデションに見舞われたが、地元ホームコースの新鋭、23歳の宮本留吉と、兵庫・舞子でプロゴルファー第1号となった33歳、福井覚治がともに161で首位を分け、後日のプレーオフで優勝を決することになった。宮本と福井は午前の第1ラウンドを、ともに80、午後81と一歩もゆずらず、改めて7月10日、同コースで、36ホールストロークプレーで争うこととなった。なお、越道政吉(甲南)は首位とタイでホールアウトしたが、午前の18番のウオーターハザードの処置ミスが発覚、失格となった。首位から5打差の3位には関東から遠征した横浜・根岸の関一雄、4位には関東、東京GCの安田幸吉、5位は兵庫・鳴尾の村上伝二が入った。
プロ第1号福井覚治が記念の第1打

日本プロゴルファー第1号 福井覚治のスイング
日本プロゴルフ殿堂
10時5分記念すべき第1打をプロゴルファー第1号、33歳の福井が放った。当時流行のつばのついた帽子。白いシャツ、紺色のニッカボッカ。手にしたドライバーはヒッコリーシャフトだ。続いて関東から遠路やってきた、安田が続いた。ハンチングを目深にかぶった21歳。白いシャツの上に大会出場の激励会で送られたカーディガン姿が初々しかった。
大会は2人ひと組で3組がスタートした。ニッカボッカに白のシャツにネクタイ姿の越道は日本で2番目のプロゴルファーだ。同組の横浜・根岸の関は無帽。雨に濡れた黒髪が強い意気込みを現して若々しかった。3組目は兵庫・鳴尾の村上。慶大出の野球選手出身。アマとしてプレーしていたが、大会前にプロ入り。それも自分から宣言してプロになったという、異色のキャリアの持ち主だ。そして最後を飾ったのはハンチングもりりしい宮本だ。ホームコースのホストプロはパワーと旺盛な闘争心で優勝候補の筆頭。栄光のトリを務めて堂々とふるまった。
ハンチング、つばの広いハットに雨用のマント姿の役員たちやメンバーが当時のゴルファーのスタイルで見守った。「ナイスショット」「グッドラック」賞賛と激励の声、拍手に力と愛情がこもった。日本のプロ競技の新しい一歩を誰もが重く受け止めた。みんな、誇らしかったに違いない。心地よい緊張感がコースを覆っていった。
「プロだからノータッチでやれ」に選手はびっくり
スタート前にこんな一幕があった。「大会はすべてノータッチで行う」と緊急の取り決めが発表されたのだ。
説明がいるだろう。こんな事情だ。当時のラウンドはショットのとき芝の上にボールをプレースした。いまと違いコースはまったく異なったコンデションだったのがその理由だ。コースはどこも新設で芝ツキは悪くボールは土のむき出す低いところに止まるため、ローカルルールで拾い上げ芝の上に置く、プレースが常識だったのだ。推測だが、各クラブの競技でもこのルールで行われることが多かったのだろう。今回の開催コース、茨木も前年、18ホールへの改修工事が済んだばかり。プレースルールは当然実施されると誰もが思っていたようだ。だが、役員は意気込んでいた。協議の結果、ノータッチで行こう。当然の決定だった。そしていま思うとこの決断は歴史的には正しかった、といえよう。なぜなら長い歴史をきざんだ今も、その時のルールは生きているからだ。当時特別ルールでやっていたら、のちにこの第1回大会が認められたかどうか、多少の懸念が残ったことだろう。
しかし、緊張と興奮に震える選手にはショックだった。表情は硬く不満だった。
宮本がその回想を、自著「ゴルフ一筋」に記す。「さて、試合が始まろうという段になって競技委員長が、君たちはプロなのだからノータッチでやれ、という。これは大変なことになったと思った」という。「茨木のコースはまだ芝ツキが悪かった。芝をところどころに植え、それが広がるのを待っていた時期だが、まだ芝は密生しない。それで普段はプレー時にはボールを芝の上にプレースしてやっていた。だが、これは試合だからノータッチで、と言われた。我々には厳しかった」。
当時は関西には芝を売っていなかった。東京からわざわざ取り寄せた芝は貴重で高価。まばらに植え根づくのを待っていたのだが、大会開催が急に決まったこともあってコンデションは決してよくなかった。普段のプレーは土の上に止まると芝の植えにおいてプレーするのが普通のことだった。選手たちは練習ラウンドもそうしたから、「ノータッチ」と当日言われて驚いた。だが、役員は初のチャンピオンシップだ、当然のことだと言った。競技全盛のいまの時代ならあたりまえなことも、なにしろ何もかも初めてのことだ。欧米の競技を手本に初めて行うプロの試合だ。プロは従うしかなかった。厳しい試練が待ち構えていた。
スタート直後、雨は強くなった。「総じてフェアウエーは重く、ランがなく、グリーンまた重く、スリーパット続出する」大阪毎日新聞の記事はそう伝える。いろいろとあったが、公平の理念にはなんら触れない。みんな同じ状況なのだから従うまで。選手たちはすぐ切り替えた。厳しい荒波の海に漕ぎ出した。
関東のホープ安田幸吉いきなり10の大たたき
いきなり不運に見舞われたのが関東からやってきた大会最年少の安田だった。2番でティーショットを林に入れると脱出に何度も手間取り10の大たたき。アウトを49と完全に打ちのめされた。
東京GCの初代プロでこの大会を機にその後あらゆる歴史上のシーンに登場する安田は関東のホープだった。5月のある日、役員室に呼ばれ大会出場を命令されている。「プロの大会があることを初めて聞いたが、横浜より遠くに行ったことがなかった。同じ関東に関一雄というプロがいることもその時初めて聞いた」という。大会には家族や親せきと水杯をかわし、東京駅からバンザイに送られて東海道線の特急で11時間余をかけて関西入りした。しかし、スタートして30分も立たないうちに10の大たたきで鼻先を折られた。95のワーストスコアで優勝争いから脱落してしまった。
宮本と福井、そして越道の関西勢が強かった。宮本はアウトを2オーバーの38で飛ばした。2番手に付ける越道に3打差、福井と関に4打をつけた。しかし、インに入ると13番でダブルボギーの7をたたき調子を落としてインは42の計80。
アウト不調だった福井覚治はインに入るとショットがまとまり始め宮本をとらえた。11番はボギーとしたが、12番バーディー、13番でボギーをたたき後退したものの、その後、パーを積み重ね18番をボギーとしながら38、トータル80で首位をキープした。トーナメントは第1組、晴れの第1打を放った福井と最終組最後のスターター宮本が首位で並んだ。
1打差の2位には越道が食い込んだ。この日、好調でアウトを41で通過するとインは17番まで通算7オーバー。最終のロングホールをパーなら70台のスコアが期待されたが、グリー前のウオーターハザードに打ち込みダブルボギーは惜しかった。トータル81で首位を逃し、福井覚治、宮本に次いで1打差の3位となった。
越道は六甲の少年キャディー大会の常連で、福井を生んだ海に近い青木(おうぎ)村の出身。二人は幼馴染だ。越道はキャディーを卒業すると福井の家に隣接してできた横屋コースで働く福井と常に行動をともにした。横屋が買収され放置された跡地で福井が室内レッスン場やクラブ修理・制作の工房を開設すると弟子となり、そこが1922年甲南GCとなると第2号のプロとなった。生年が不詳。しかし、福井とは2,3歳下、大会当時は30から31歳と推定される。
そしてもうひとり。宮本だ。ホームコースの利を生かしアウトを38で大会をリードするとインは13番でOBにするダブルボギーの7などインは3OBと乱れたが、42、トータル80で第1ラウンドを終えた。首位は福井、宮本が80でトップを分け1打差で越道、5打差4位に関、7打差5位が村上、そして安田幸吉は15打差の6位と出遅れた。関西勢はいかんなく地元の利を生かした。
午前18ホールの成績は次の通り
| 1 | 福井 覚治 | 42 | 38 | 80 |
| 1 | 宮本 留吉 | 38 | 42 | 80 |
| 3 | 越道 政吉 | 41 | 40 | 81 |
| 4 | 関 一雄 | 42 | 43 | 85 |
| 5 | 村上 伝二 | 46 | 43 | 89 |
| 6 | 安田 幸吉 | 49 | 46 | 95 |
後半の18ホールは午後2時半スタート。選手、役員そしてメンバー、オープン観客らは着替えをし昼食で腹ごしらえをした。大会後半の模様は次項に続く。