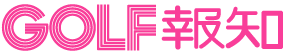記念すべき日本オープンの第1回大会は1927(昭和2)年5月28、29日、神奈川県横浜市の程ヶ谷カントリークラブ(6170ヤード、パー72)で行われた。参加したのはアマ12人、プロ5人の計17人。アマはハンデ8まで、その2年前に発足した日本ゴルフ協会(JGA)加盟クラブの推薦者に限られた。ということは当時の8までのアマは20人くらいしかいなかった、と推測される。ついでながら日本オープンより20年も前にはじまった日本アマの出場者はハンデが15までだった。オープン競技といいながらいざ始まるとなると厳しい出場基準となったのは皮肉だが、第1回大会だ、関係者にも力が入っていたことがうかがえ、緊張感が伝わってくる。
アマの出場者は赤星四郎、六郎兄弟、川崎肇(いずれも程ヶ谷)大谷光明、井上信(東京)ら。プロは関東の安田幸吉(東京)関一雄(横浜・根岸)浅見緑蔵(程ヶ谷)、関西から宮本留吉(茨木)中上数一(京都)の5人。プロは当時、コース認定は8人だけ。全員揃わなかったのは所属コースの許可が出なかったり、前年の関西オープン優勝の福井覚治のように乞われて朝鮮へレッスンにでかけて日本にいなかったためだ。
賞金は優勝300円、2位150円、3位100円
大会は1日36ホール、2日間72ホールのストロークプレーで争われた。優勝賞金は300円、2位15円、3位100円。当時の公務員の初任給が付き50円くらいだからプロにとっては魅力のある賞金額だった。大会規定で36ホールを終わって首位から20ストローク以上離されると最終日の決勝ラウンドに進めなかった。
快晴に恵まれた第1日午前、赤星四郎が74で首位に立った。2位は弟の六郎と浅見緑蔵が79で続いた。同日午後、四郎が90と大きく後退した。10番のパー3でOBを出し8もたたいた。変わって六郎が73のベスト・スコアをマーク、通算8オーバー、152で首位に立つ。2位は浅見が6打差で続いた。首位から20打差までの7位まで、アマ3人とプロ4人の計7人が翌日の決勝ラウンド54ホールへ進出した。
六郎は最終日も好調で午前79、通算231で2位に上がった宮本に11打差。浅見には12ストローク差をつけた。昼食をはさんだ最終ラウンド、六郎は78とまとめ、通算309でホールアウト、浅見が追い上げたが、10打差の319、宮本は320で3位、4位には四郎が入った。六郎は4ラウンド70台で当時としては驚異の好スコアだった。
第1回日本オープンが開催された1927年はアメリカでスチールシャフトの使用が公認されたばかりであった。
栄えある初代チャンピオンはアマチュアの頭上に輝いた。「当時の朝日新聞は「2等浅見緑蔵、3等宮本はプロフェッショナルだけに、赤星氏の優勝は偉大である」と讃えた。アマチュアの優勝はこの時以来、日本オープンにはない。大会の歴史が刻まれるたびに六郎の名は尊敬と驚きで語りつがれている。
天才赤星六郎はアメリカ育ち大スター
しかし、当時のゴルフ界は赤星の快挙を当然の結果として受け止めた。4位に入った兄・四郎とともに赤星兄弟は、輝くばかりの光をゴルフ界の隅々まで与えていたからだ。中でも二人はボビー・ジョーンズ時代のアメリカでゴルフを覚え六郎は1924年、米ノースカロライナ州パインハーストで行われた全米アマチュア・トーナメントの一つ「パインハースト・スプリング・ミーティング・トーナメント」で優勝した。大会は全米のトップクラス319人が出場し36ホールを争う予選を5位で通過、マッチプレーのファーストフライト(第1グループ)で次々と勝つと、決勝で前年覇者のドナルド・パーソンを4アンド1で下した。26歳だった。
六郎は19歳で渡米、ニュージャージー州のロレンスビル高を経てプリンストン大へ。ゴルフ部に入るとのちに全米オープンに勝つシリル・ウオーカーに教えを受けるなど英才教育を受けた。パインバレーなど名門コースのメンバーとして一流の雰囲気の中でしっかりアメリカンゴルフに溶け込んでいた。
四郎もその数年前に同じ道を歩みペンシルベニア大でゴルフを覚えニュージャージー州のシャカマクソンCCで専属プロのボビー・クルックシャンクからゴルフを習った。1924年には地元の「プリンス・オブ・ウエールズカップ」で優勝している。この快挙はあまり知られていないのは、地元の試合だったことと、弟の六郎の優勝があまりにも大きな事件だったことで、過小評価されたのだろう。
鹿児島の薩摩藩の郷士、父・赤星弥之助は鹿児島県の洋学者、磯永孫四郎の子として生まれ東京に出て赤星家に養子に入ると実業家としてロンドンにわたった。そこで世界的な兵器会社が日本に独占販売の代理店を置きたい、との要望を受け引き受けたことから巨利を得た(「ゴルフその神秘な起源」井上勝純著・三集出版)。
弥之助は五男三女を得て51歳で没したが、兄弟は国際人としての素養を身に着けるため次々に渡米した。赤星兄弟は男が5人いて五郎を除き4人が中学を出ると8年間のアメリカ留学を経験している。赤星家のスポーツにおけるルーツである。四郎はペンシルベニア大ではゴルフよりアメリカンフットボールに取り組んでいる。ゴルフは日本に帰国してからの方が熱心だった。
日本のトッププロ安田、浅見、宮本を育てた赤星兄弟
1925年、六郎は帰国すると四郎とともに東京GC、程ヶ谷CCのメンバーとなり安田幸吉、浅見緑蔵らを育てる。のちに茨木に招かれ宮本留吉を指導すると宮本は東京GCに半年間、“留学”レッスンを受けた。茨木のメンバーが「技術をおそわってこい」と送り出す、そんな時代だった。
六郎は宮本にはジーン・サラゼンと同じ、左親指を外すインターロッキング・グリップを、大柄な浅見にはオーバーラップ、小柄な安田にはインターロックを教え、東京GC内にプロショップを設けるなど専属プロとしての身分確立に手を差し伸べた。3人は生涯そのグリップで通した。
初めての日本オープン。しかし、勝負となると師だ、弟子だといっていられない。コースにでれば目の前のボールを必死でたたいて1打でもよいスコアを目指すのがゴルファーである。アマ赤星の優勝にプロたちは歯噛みして悔しがっていたことをここで紹介しておこう。プロたちの闘争心は決して軟弱なものでなかったことを歴史が伝えるこんなエピソードがある。
最終日、最終ラウンドの9番ホールのことである。宮本がフェアウエーバンカーからようやくボールをグリーンオンしてホット一息ついた直後だ。「ちょっと待て」と同伴競技者の四郎から声が飛んだ。「バックスイングの時、クラブのソールが砂に触った、ペナルティーだといわれたが、初めてのことでどうしたらいいのかわからず混乱した」とあわてたのは宮本。協議の結果、宮本には2罰打が付き2位で上がったのに浅見に抜かれて3位に下がった。第1回大会で有名な「おい宮本、ちょっとまった」事件である。
浅見にも最終日の第3ラウンドの5番でこんなことがあった。ティーショットは深いラフに入ったが、3分もすると優勝争いをする六郎から「緑蔵、もう5分過ぎたぞ。うち直してこい」慌てふためいた浅見はこのホール7をたたきそのラウンドで85をたたいた。「おしなべて当時のプロは、旦那衆であるアマチュアの邪魔にならぬように心がけ、もっぱら遠慮がちにプレーしなければならなかった。宮様とか、実業家とか、外交官など貴顕紳士の中にあって、目立たぬように小さくなってプレーをしたものである」後日出版した回顧録「起伏の男道」菅原栄二著(廣済堂)に記している。
黎明期のプロたちは、確かに赤星兄弟から多くを学んでいる。2,3人の例外を除いてほとんどのプロが、多かれ少なかれコーチを受けていたことは紛れもない事実であり、とりわけ六郎には“天才”という熱い思いも寄せていた。それゆえに、プロたちは競技会でもイニシアチブをとれず、アマチュアたちからいいようにあしらわれた面もあるのだ。
浅見はこうも述べている。「赤星六郎さんとの10打差は、自分としては納得のいかないものでした」 何が真実かではない。時代だったのだ。そして、そんな時代があって次があり、今がある。