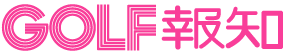こらえていた涙は18番のティーショット前に瞼を重くした・・・。
キャディに励まされショットをフェアウエーに運んだが、おそらく景色はみえていなかっただろう。セカンドショットをどうにかグリーンオン、放物線を描く強烈なファーストパットを80センチに寄せるパーに万雷の拍手。誰もが総立ちだ。その渦の中、トム・ワトソンは白い歯を見せながら、大きなこぶしで、目を何度も何度もこすった。
マスターズ2回優勝のトム・ワトソンが9日の第2ラウンドを最後にマスターズトーナメントから姿を消した。77,81年チャンピオンも66歳の年齢には勝てなかった。2日間、8オーバー、予選カットラインに2打及ばなかった。22歳のスピース、24歳松山ら若者の陰で往年の名手たちが姿を消すのは勝負の世界のならい。だが、この日のオーガスタの観客は、その後ろ姿に万感の想いを込めた。暖かい拍手はいつまでも鳴りやまなかった。
マスターズはこれまでも多くの先人を送り出してきたがパーマー、ニクラウス、そしてワトソンは特別だ。なぜなら3人の誕生年はパーマーが1929年、ニクラウス1940年、そしてワトソンが1949年。まるで天が意図したかのように10年周期。(そう、ニクラウスは40年1月の早生まれだ)。その雄姿は絶え間なく、それどころか厚みを増しながら綿々と40数年をつないできた。
3人のピークは10年というエポックで合致することなく続いた。“キング”パーマーをニクラウスが追い、その帝王の座をワトソンがつなぐ3巨頭時代。それが世界に冠する米ツアーの魅力だった。
“末っ子”のワトソンは1971年、ヤングライオンズと呼ばれた若者集団の、だが、特に目立たない一人としてデビューした。赤毛に小柄、176センチはスターになるには小さく、ニックネームは“トム・ソーヤ”。マーク・トウェインの冒険小説の少年主人公からついたのが由来、みんな、可愛い坊やだね、頑張るんだよ、という程度の期待度。だが・・・・。
トムが新帝王になったのはマスターズがきっかけとなった。1977年、大会5度の最多優勝(当時)のニクラウスを終始リードして逃げ切った。75年の全英オープン(ターンベリー)で二人は激戦を繰り広げワトソンが勝ち新帝王と言われたが、このマスターズをもってその座を固めたのだ。81年、ワトソンは再びマスターズでニクラウスと相まみえ、さらに奇跡の男ミラー、新人のノーマンを下した。
玉にキズはつきもの。ワトソンはついに全米プロのタイトルはとれていない。こんなエピソードがある。初優勝が全米プロのジェフ・スルーマンという小柄で強いアメリカ人プレーヤーがいる。この10歳ほど年下の男を何かと可愛がっているワトソンはある日「僕の全英オープンのタイトルを2つあげるから全米プロのタイトルを僕にちょうだい」といった。この話、もう米ツアーでは有名だ。
ワトソンはジョーク好きで知られる。だが、ちょっぴり本音が入っていて面白く、人柄も手伝って好きな話だ。PGAツアー39勝のうちメジャーは、全英オープン5勝のほかマスターズ2勝、全米オープン1勝。しかし、全米プロだけ勝っていないことは誰が気になるといって本人が一番気になることではある。キャリアグランドスラムという。4メジャーをすべてその生涯で手に入れたのはサラゼン、ホーガン、プレーヤー、ニクラウス、タイガーの5人だけ。そこに加われなかった。玉のキズ、なのだ。
さよなら、ワトソン。でもそれでいいのだ。この日、18番を覆った惜別の拍手と歓声は人間臭い、そんな男に贈られた親愛いっぱいの賞讃であったのかもしれない。西海岸の名門、スタンフォード大心理学科卒。流した涙は悔しさのせいではない。断じて。成し遂げられなかったものに対する懐古、その充足感の顕れなのだ。いいプレーをたくさんありがとう、と心からお祝い申し上げる。