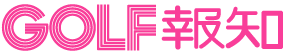日本ツアーの新トーナメント「ISPSハンダ・グローバル・カップ」は武藤俊憲がプレーオフを制し、3年ぶり、ツアー通算6勝目を挙げた。16番で20メートルのバーディーパット、17番は5メートルの大ピンチのパーパットをねじ込み、最終18番4メートルのバーディーパットを決めプレーオフに持ち込んで勝った。ここのところ全く元気のなかった日本ツアーが息を吹き返えす、久しぶりに爽快な勝ちっぷりに拍手だ。よくやった!
大きな球を打つ武藤である。“大だまを打てなきゃ今の時代、活躍できないよな”-そんな使い方、ゴルファーだけにしか通じない言葉だ。野球でいえばホームランバッターだが、ゴルフでは“力”プラス“技(繊細さ)”を持ったものへの敬称となる。スケールを表すゴルフ界だけの測定値である。武藤はドライバーが飛んで曲がらない飛距離と高いフェアウエーキープ率を誇るトータルドライビングランクのナンバーワンプレーヤーだ。大逆転、起死回生の快挙は、ちょっと遅すぎるきらいは否(いな)めないが、大きな転機になるだろう。37歳、ゴルフではこれからだ。
私的には、人もコースも状況も、すべてに思い通りの展開だ。コースは太平洋マスターズでおなじみ、加藤俊輔氏設計のヴィンテージGCだった。1995年開催の「ダイワインターナショナル」以来のツアー開催。富士を望む静岡の御殿場に太平洋御殿場コースを造った加藤氏が、日本アルプスを望む山梨の雄大な自然にどんなコースを造ったか、という興味本位な見方が当時、話題。ふたをあけると大会には25歳だったフィル・ミケルソンが婚約中のエミー夫人を連れて参戦した。優勝したのは“ガッツ男”安田春雄の弟子の森茂則。ミケルソンは確か日本ツアーデビューでとまどいもあったか、平凡な成績に甘んじたが、婚約者をいたわりながらも生来の真面目さ、必死に戦っていた姿が印象に残る。

そんな感情移入のある大会。今回、興味深かったのはイアン・ポールター(英)らPGAツアーの面々が大挙参戦したことだ。13年全米プロ優勝ジェイソン・ダフナー(米)。マスターズVのカール・シュワーツェル(南ア)は全米オープン、あのチェンバースベイの興奮をそのまま持ち込んだ。
セントアンドリュースを起伏だらけの採石場跡地に持ってきたロバート・トレント・ジョーンズ・ジュニアは正しかったのか、間違っていたのか。今、ゴルフ界を真っ二つに分ける議論沸騰のあの大会。
ポールターはチェンバースベイでは、出ては打たれ連日上位と下位をエレベーターのように上下、最後へとへとになり下位に沈んだ。が、時差ボケ、疲労こんぱいの山梨では優勝争い。2打差の4位はやはり世界トップランカーの迫力だった。 言うまでもなく“大ダマ”を駆使していた。その上、あのパットのうまさは強気と経験のたまものだ。武藤より2歳上の39歳。あの闘争心とともに学んでほしい選手だ。谷口徹が日本での師なら世界をにらんでポールターに弟子入りだ、学んでほしい。
6勝目の翌朝、電話で話した。―地にへばりつく青木のようないいパットだった、というと「青木さんには大事なところで、技術が、ラインがと考えていたら勝てねえ、といわれた。勝ちたきゃまっすぐ打つんだよ。それ以外、ねえだろうが、と。今回、それを感じた」。-初めてだね、競り合って勝ったのは。「そう、前の方で気楽にやれて結果、逆転勝ちが俺のスタイルといい気になっていた。プレッシャーの中、今回はコースマネジメント、キャディーとの対話の中でやるべきことをやっていく読みと実践がしっかりできた。自信になった。これから生きる」そして最後の方の言葉は今後の武藤を占うのには格好の材料になると思った。

「孔明(小田)が賞金王になったのですからね。僕もかわらなきゃいけない」―。目標が見えた。闘争心がめばえなければこんなことをいうことはなかった。
大会初日のスタートの選手紹介で「むとうよしのり選手です」とサッカー・FC東京から独・ブンデスリーグ、マインツ入りの時の人、武藤嘉紀と混同されてしまった。「よしのり」と「としのり」。どっちも頑張ってほしいが、当面、「今年の賞金王がノルマだね」とプレッシャーをかけておいた。賞金王なら世界も開けるし、そうなれば間違えられることもなくなるだろう、冗談のつもりだった。いつものように笑ってごまかされるのを覚悟していたら、返事は返ってこなかった。期待が募った。